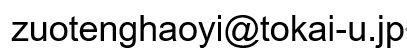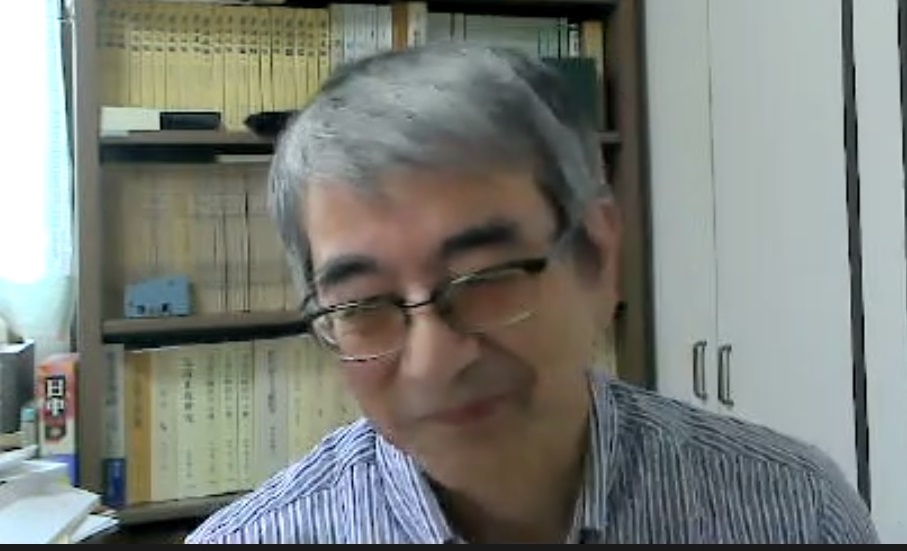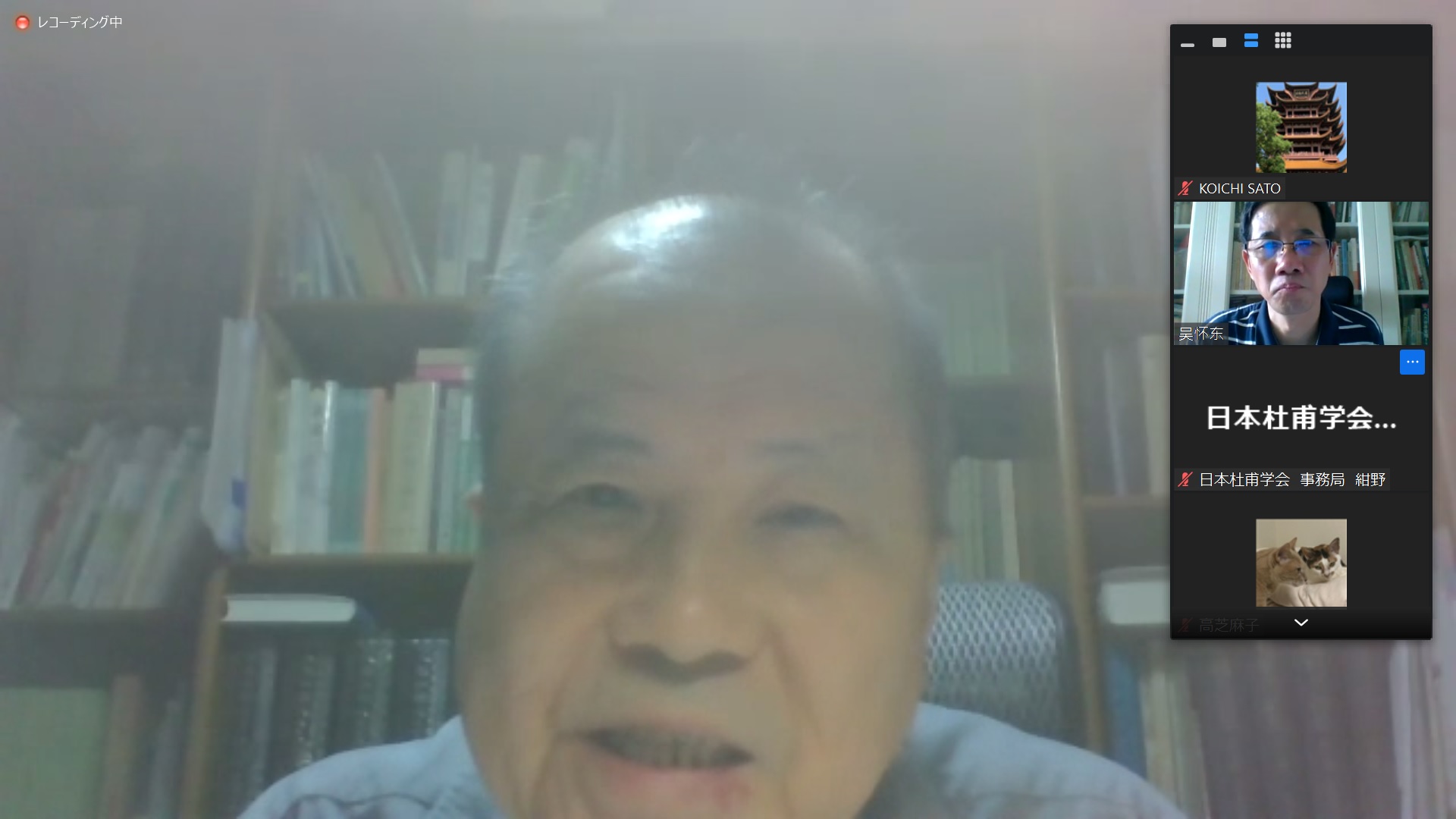- 第8回 日本杜甫学会大会のお知らせ
- 会 場:横浜国立大学教育学部6号館102 zoomを用いたオンラインとの併用
〒240-8501 横浜市保土ケ谷区常盤台79番2号
zoom アドレス については申込みされた方にお知らせします。
日 程: 2024 年 9 月 6 日 ( 金 ) 14時開始
※感染状況ならびに会場校の判断により、全面オンライン開催となることがあります。
※大会の参加の出欠・参加方式(対面・オンライン)について、formsよりお知らせください。
13 時 30 分 受付開始
13 時 50 分 開会の挨拶
研究発表の部(14:00~14:40)
題 目:銭謙益と杜詩詳註――清代禁書とその疎漏
発表者:佐藤浩一(東海大学) 発表資料 別表PDF
(質疑応答をあわせて40分)
14 時 40 分~14 時 50 分 休憩
シンポジウムの部(14:50~16:10)
テーマ:教材としての杜甫の詩
登壇者:三上英司(山形大学)
高芝麻子(横浜国立大学) 発表資料
大橋賢一(北海道教育大学) 発表資料
潮田 央(神奈川県立総合教育センター) 発表資料
16 時 10 分~16 時 20 分 休憩
16 時 20 分~16 時 50 分 総会
※学会全体の懇親会は実施しません。
※評議員会は大会開催の1週間前にメール審議で行います。
大会に関する情報は、X(旧Twitter)でも発信中です。
日本杜甫学会事務局 battanアットマークwaseda.jp(担当 紺野達也)
- 第7回 日本杜甫学会大会
- 以下のとおり、第七回大会が行なわれました。
会場:北海道教育大学旭川校(P103教室(P棟1階)) zoomを用いたオンラインとの併用
日程: 9月 2日 ( 土 ) 13時20分開始
13 時~ 受付開始
13 時 15 分~ 開会の挨拶
研究発表の部(13:20~14:40)
1.題 目:李白の閨情詩―閨情・閨怨の百花開く 発表資料
発表者:下定 雅弘(岡山大学)
2.題 目:杜甫詩対偶素の提唱 発表資料
発表者:水谷 誠(所属なし)
※本発表に関連するデータベース「杜甫対偶素」は、中国詩文研究会ウェブサイトでも公開しております。
(質疑応答をあわせて一人40分)
※14時40分~14時50分 休憩
シンポジウムの部(14:50~16:20)
テーマ:杜甫の散文について考える―杜甫文学の全体像を明らかにするために―
パネリスト:谷口 匡(京都教育大学) 発表資料
高橋 未来(大阪公立大学)発表資料その1 その2
荒井 礼(宇都宮大学(非))発表資料
司 会:谷口 真由実(長野県立大学) 発表資料
(発表 60分・質疑 30分)
※16時20分~16時30分 休憩
16時30分 ~17 時 総会
※学会全体の懇親会は実施しません。
また、評議員会は大会開催の1週間程度前にメール審議で行います。
大会会場 北海道教育大学旭川校(P103教室(P棟1階))
〒070-8621 北海道旭川市北門町9丁目
大会会場へのアクセス
【JR旭川駅から】
旭川電気軌道バス「5番旭町・春光線」で15分、バス停「旭町2条10丁目」下車、徒歩5分
旭川電気軌道バス「14番旭町線」で15分、バス停「旭町2条10丁目」下車、徒歩5分
旭川電気軌道バス「24番新橋・北門線」で15分、バス停「北門9丁目」下車、徒歩5分
【朗報】当日、旭川では市内バスが無料開放となっているそうです。
c
《日本杜甫学会 事務局》
〒259‐1292神奈川県平塚市北金目4‐1‐1
東海大学語学教育センター 佐藤浩一研究室
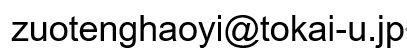
- 第6回 日本杜甫学会大会
- 会 場:京都女子大学(J校舎 J003多目的ホール) zoomを用いたオンラインとの併用
日 程: 9月 10日 ( 土 )
研究発表の部(14:00~14:40)
題 目:「行雲流水」と杜詩
発表者:鳴海 雅哉(函館工業高等専門学校)

- シンポジウムの部(14:50~16:50)
「安史の乱は杜甫に何をもたらしたのか」
パネリスト:
好川聡 (岐阜大学)「自京赴奉先県詠懐五百字」以降の杜甫詩の展開について
遠藤星希(法政大学)杜甫の詩における「山河」の在り方とその変質について――安史の乱の前後を中心に――
高芝 麻子(横浜国立大学)杜甫の月が照らすもの司会:大橋 賢一(北海道教育大学旭川校)
司会:大橋 賢一(北海道教育大学旭川校)

- 第5回 日本杜甫学会大会
- 2021年9月4日(土)14時より、オンライン(zoom)にて第5回大会を実施しました。
研究発表の部(14:30~16:00)
題 目:杜甫韻字ユニットの継承とその影響について
発表者:水谷 誠(創価大学)
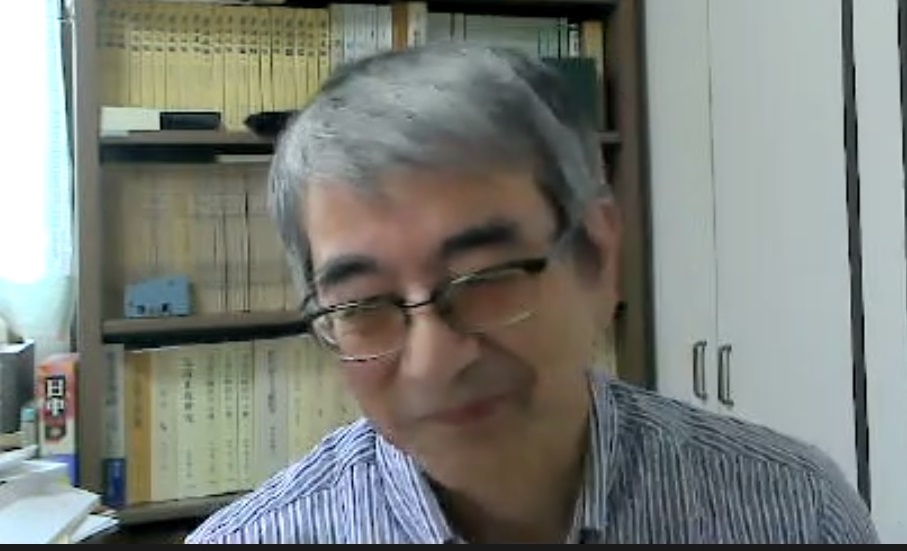
題 目:杜甫詩における閨情表現
発表者:下定 雅弘(岡山大学)
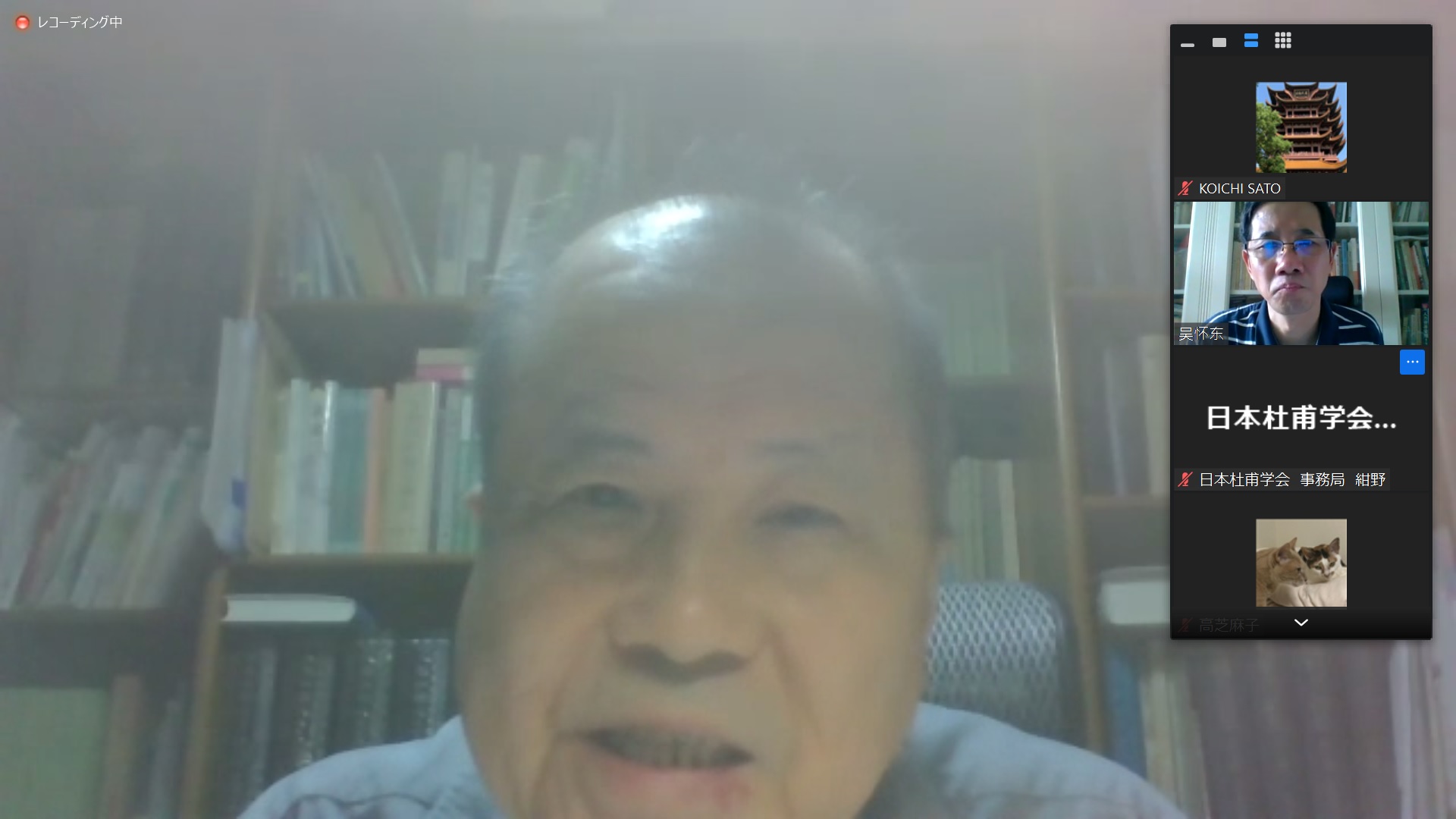
講演の部(16:10~17:10)
題 目:《秋日夔府詠懷奉寄鄭監李賓客一百韻》―兼論其創作過程與寫作特點―
発表者:呉 懐東(安徽大学)

-
- 第4回 日本杜甫学会大会
- 本年、九月に予定されていた第四回大会は、新型コロナウィルスの流行とそれに伴って生じている社会的情勢を鑑み、中止と致します。
総会については、どのような方法で開催することができるか、理事会・評議員会で議論しております。それにつきましては決定次第、本ホームページでご案内致します。
- 第3回 日本杜甫学会大会
- 第3回日本杜甫学会大会が、9月7日(土)に、
神戸研究学園都市 大学共同利用施設UNITYにて行われました。
題 目:杜甫と高適の制挙受験について
発表者:田中 京(立命館大学(院))
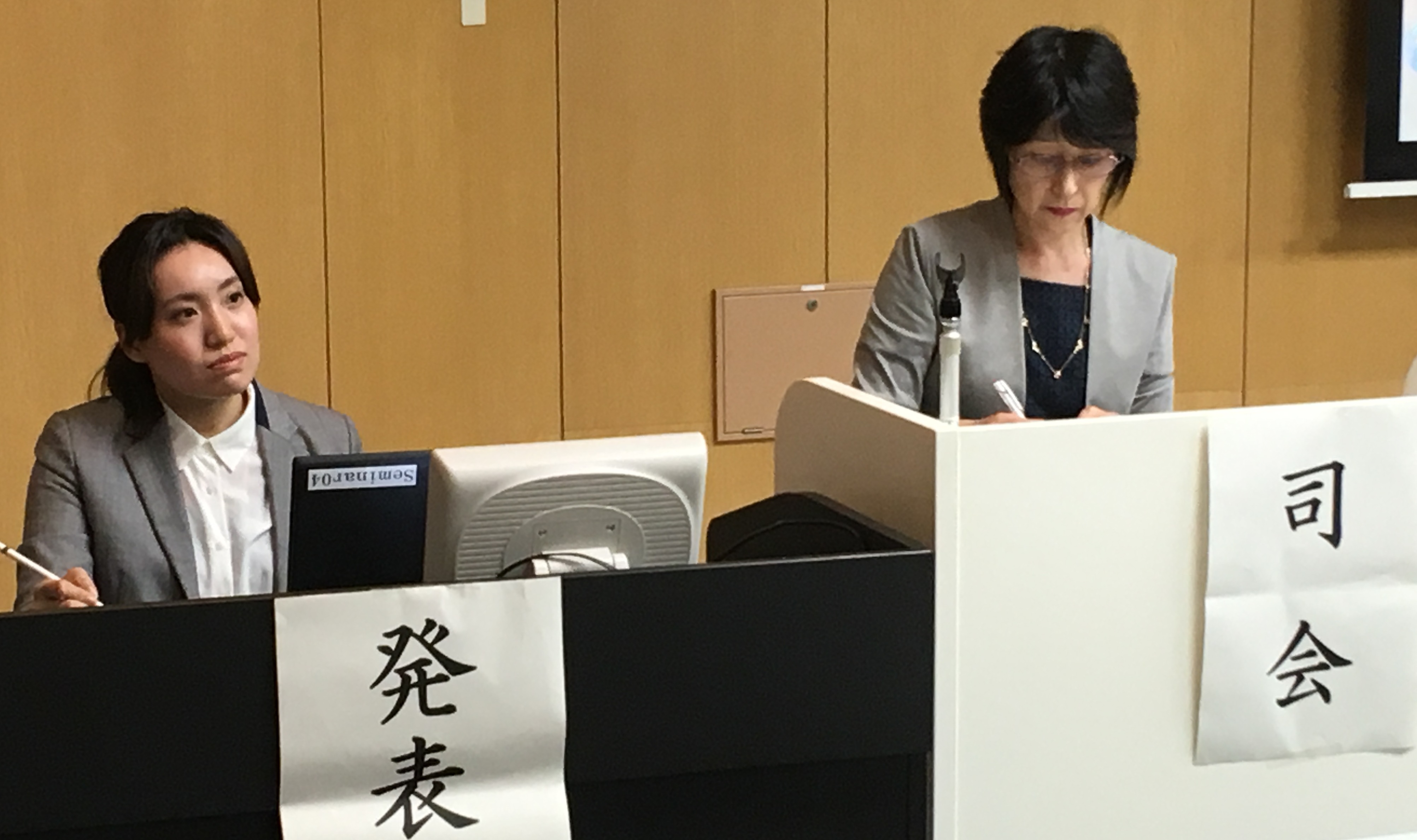
題 目:杜甫“大庇”思想對東亞建築民俗文化的巨大影響——以緝考韓國“上樑文”文獻為中心
発表者:沈 文凡(吉林大学)

題 目:杜甫と門閥意識
発表者:松原 朗(専修大学)
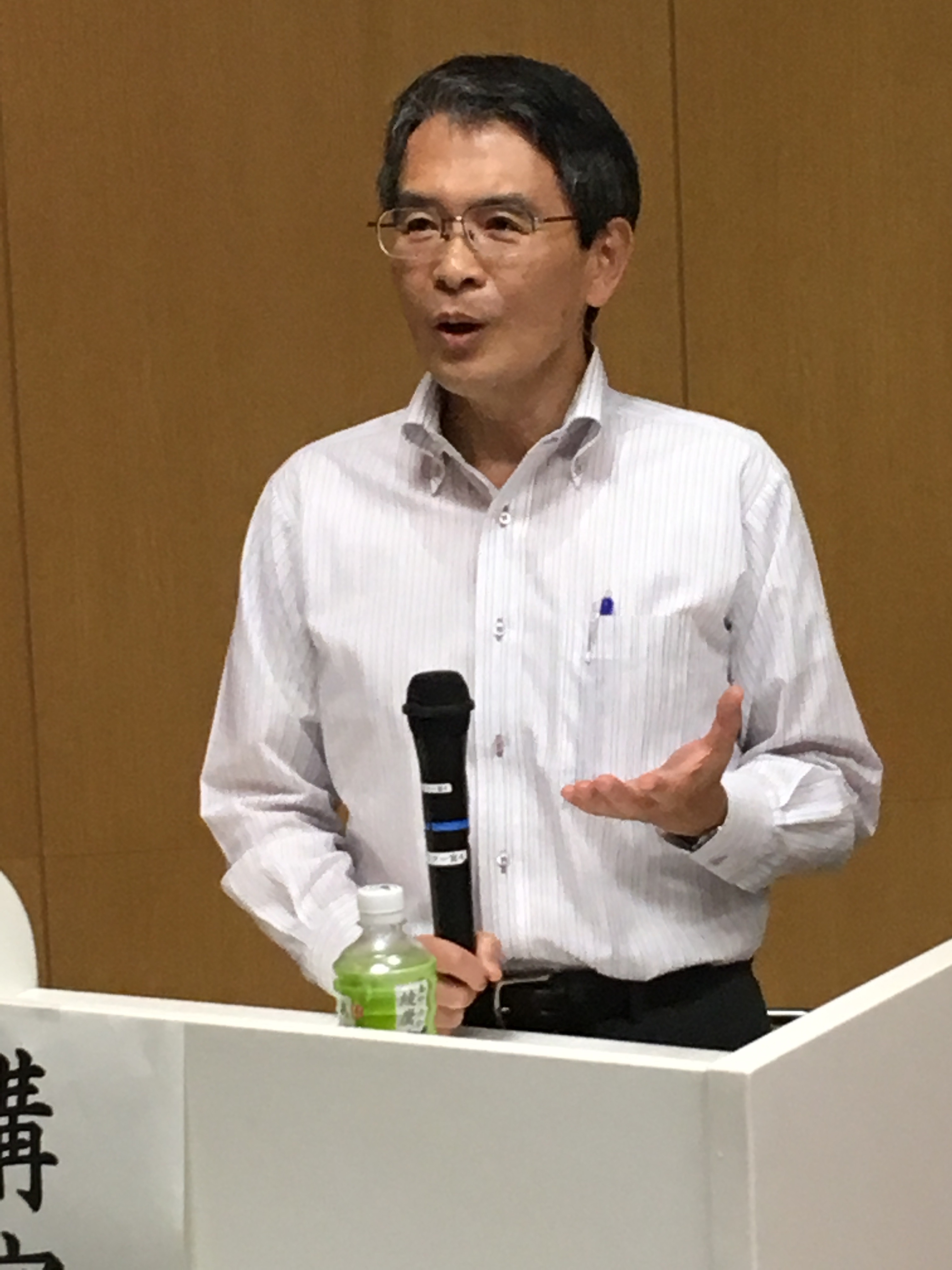
-
- 第二回 日本杜甫学会大会
- 2018年10月5日(金)早稲田大学9号館第一会議室にて、
日本杜甫学会 第二回大会が行われた。
- 「薛濤と杜甫 ― 時を異にして成都の浣花渓に居住した二人の詩から ―」
発表者:横田 むつみ(お茶の水女子大(院))
司 会:松原 朗(専修大)

-
- 清・顧宸『辟疆園杜詩註解』について
発表者:大橋 賢一(北海道教育大旭川校)
司 会:甲斐 雄一(明治大)

-
- シンポジウム 再読『李白と杜甫』
パネリスト:張 思茗(復旦大)
下定 雅弘(岡山大)
※登壇予定であった査屏球教授(復旦大)と 呉懐東教授(安徽大)は、都合により欠席。
査教授の推薦で、張思茗氏が登壇した。
下定会長は「杜甫的“獨善”―兼論其對仙境、仙道的憧憬― 」という観点から、
張思茗氏は「阆州隶属之变与杜甫阆州之行」という観点から発言した。

- 《日本杜甫学会 事務局》
〒259‐1292 神奈川県平塚市北金目4の1の1
東海大学国際教育センター 佐藤浩一研究室
![]()